マルコムは早速エプロンをかけて、ムール貝の調理を始めた。
深い圧力鍋を熱し、ムール貝とパセリの茎を入れ、白ワインをかけて蒸すのだ。
直径10センチもあるムール貝はボリュームたっぷり。
蒸し上がって開いた貝からオレンジ色の肉がふっくらと覗いている様子は、未だに夢にも出てくるほど素晴らしい。
驚くほどシンプルな料理だったが、バゲットと白ワインによく合い、すごく美味しかった。
日本のカラス貝と似ているが種類は同じなのだろうか?
【第1話はこちら】
食事での会話
食事をしながらいろいろなことを話した。
主にマルコムが語った。
3歳のとき母親を亡くし、ほとんど寮で暮らしたこと(イギリスにはボーディングスクールといって全寮制の学校がたくさんあるのだ)。
卒業して下級官吏として人生をスタートさせた。
友達のパーティーで出会った前の奥さんはフランス人で、やはり若いときに母親を亡くしていた。
似た境遇だったこともあって恋が芽生え、結婚。
ふたりの間には男の子がふたり生まれたが、奥さんに好きな人ができて出て行ってしまい、5年間かけて離婚したこと。
サッチャー政権で公務員の大量リストラがあり、ウエストミンスター区の外郭団体に勤めていたマルコムもまた、その対象となった。
その団体自体が他の部署に吸収されてしまうことになったのだ。
長男の大学の学資が必要だったから1年間粘ったけれど、結局職場で「いじめ」のような目にあって早期退職をしたこと。
私には彼がものすごくついてない人に見えた。
退職以来、慎ましいながら気楽な生活を送っているようだったが、人生のパートナーは子どもたちが置いていった黒い老いたメス猫の「マジック」だけ。
この18世紀のがんこな老貴婦人を思わせる黒猫は、最初から私に対し、敵意と嫉妬を隠そうともしなかった。
あっという間に時間が過ぎた。
食事とはなんて効果的なデートだろう。
美味しい料理は心も体も温める。
ほっこりした気持ちで心を開いて話ができ、距離が縮まる。
抑えきれないさびしさ
夜9時近くなったので、
「ごちそうさま、そろそろおいとまします」
席を立とうとした私にマルコムは言った。
「Emma、お願いだから、あと30分だけここに一緒にいてくれないか?」
寂しそうな顔だった。
下心は微塵も感じられなかった。
でも、やはり最初の訪問なんだし、私の寮の周辺は治安も悪い。
後ろ髪を引かれる思いで、私はやはり帰宅することにした。
「ごめんなさい、やはり今日は帰ります」
そう宣言すると、それ以上マルコムは私を止めなかった。
寂しいんだろうな、と私は思った。
またね
マルコムは愛車ローバーで私を駅まで送ってくれた。
駅から歩いても15分とはかからない山の手にマルコムの家はあった。
車ならほんの5分。
以降、タクシーを使っても、5ポンド以上になることはない距離だった。
駅に着くと、残念なほどすぐに電車が来た。
オーピントンというこの駅はロンドンブリッジとの連絡が抜群で、快速電車がしょっちゅうやってくる。
改札口を通る私にマルコムは言った。
「ゆっくりお休み、またね」


















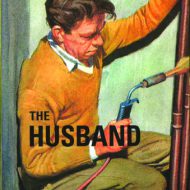



この記事へのコメントはありません。